東京・春・音楽祭-東京のオペラの森2013-
《午前11時》の音楽会 vol.3金子亜未 オーボエ・リサイタル
~第10回 国際オーボエコンクール・軽井沢 奨励賞受賞記念
春の上野で「朝活」はいかがですか?今年の《午前11時》の音楽会は、札幌交響楽団首席、期待のオーボエ奏者の登場です。同世代の仲間たちに加え。大先輩との共演で、朝にふさわしい、清々しい音楽をお届けします。
プログラム詳細
2013.4.13 [土] 11:00開演(10:30開場)※ この公演は終了いたしました。
東京文化会館 小ホール
■出演
オーボエ:金子亜未
フルート:竹山 愛
クラリネット:西川智也
ファゴット:長 哲也
ホルン:日橋辰朗
チェンバロ:桒形亜樹子
ピアノ:寺嶋陸也
■曲目
テレマン:《12の幻想曲》より 第1番 イ長調
J.S.バッハ:オーボエ・ソナタ ト短調 BWV1030b
シューマン:アダージョとアレグロ op.70
ミヨー:組曲《ルネ王の暖炉》op.205
プーランク:管楽器とピアノのための六重奏曲
【試聴について】
プログラム楽曲の冒頭部分を試聴いただけます。
ただし試聴音源の演奏は、「東京・春・音楽祭」の出演者および一部楽曲で編成が異なります。
~関連コラム~


出演者
オーボエ:金子亜未 Ami Kaneko 1990年生まれ。千葉県出身。2012年、東京藝術大学音楽学部器楽科管打楽器専攻を首席で卒業。安宅賞、アカンサス音楽賞、三菱地所賞受賞。新卒業生紹介演奏会にてB.マルティヌーのオーボエコンチェルトを藝大フィルハーモニアと共演。第79回日本音楽コンクールオーボエ部門第3位。第28回日本管打楽器コンクールオーボエ部門第1位。第10回国際オーボエコンクール・軽井沢第2位、奨励賞、軽井沢町長賞(聴衆賞)受賞。オーボエを和久井仁、小畑善昭、池田昭子の各氏に師事。12年7月より札幌交響楽団首席オーボエ奏者。

フルート:竹山 愛 Ai Takeyama
東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。同大学院修士課程修了。第26回日本管打楽器コンクール第1位、第79 回日本音楽コンクール第1位等、受賞歴多数。 東京フィルハーモニー交響楽団等、多くのオーケストラと共演。2011年「丸の内・街ブランドCD賞」受賞。同年11月、記念CD『Plays Paris』が全国発売(制作:ソニー・ミュージックダイレクト)。
© Hiro Kimura

クラリネット:西川智也 Tomoya Nishikawa 大阪府出身。大阪教育大学教育学部教養学科芸術専攻音楽コース卒業。東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程修了。第18回日本木管コンクール入選。第23回宝塚ベガ音楽コンクール第2位、併せて会場審査員特別賞(聴衆賞)受賞。第9回東京音楽コンクール木管部門第1位。日本フィルハーモニー交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団と共演。これまでにクラリネットを和田尚裕、青山秀直、山本正治の各氏に師事。小澤征爾音楽塾、サイトウ・キネン・フェスティバル松本、木曽音楽祭等に参加。その他、オーケストラや室内楽等を中心に活動している。現在、洗足学園ニューフィルハーモニック管弦楽団、N響アカデミーに在籍。

ファゴット:長 哲也 Tetsuya Cho
北九州市出身。東京藝術大学音楽学部器楽科卒業。これまでにファゴットを永江恵子、石川 晃、水谷上総の各氏に師事。室内楽を河村幹子、山本正治の各氏に師事。また、ダーク・イェンセン、ジルベール・オダン、マルク・トゥレネル等のマスタークラスにて研鑽を積む。在学中に、藝大モーニング・コンサートにて藝大フィルハーモニアとモーツァルトのファゴット協奏曲を共演。卒業時に同声会賞を受賞。木曽音楽祭、北九州音楽祭を始め、「JTが育てるアンサンブルシリーズ」等に出演。現在、東京都交響楽団首席ファゴット奏者。
© 堀田力丸

ホルン:日橋辰朗 Tatsuo Nippashi 東京都出身。12歳からホルンを始める。2010年、東京音楽大学卒業。第8回東京音楽大学コンクール管打楽器部門第1位。第26回日本管打楽器コンクールホルン部門第1位、併せて特別大賞、審査員特別賞、東京都知事賞、文部科学大臣奨励賞を受賞。第80回日本音楽コンクールホルン部門第1位、併せて岩谷賞(聴衆賞)、E.ナカミチ賞を受賞。 07~11年、小澤征爾音楽塾オーケストラメンバー。水戸室内管弦楽団、JT主催「JTが育てるアンサンブルシリーズ」、10年ヤマハ管楽器新人演奏会、アレキサンダーホルンアンサンブルジャパン演奏会、NHK-FMラジオ番組「リサイタル・ノヴァ」、12年、木曽音楽祭にそれぞれ出演。これまでにホルンを後藤照久、井手詩朗、水野信行の各氏に師事。

チェンバロ:桒形亜樹子 Akiko Kuwagata
ドイツ国立デトモルト音楽大学、シュトゥットガルト音楽演劇大学卒業、国家演奏家資格を取得。現代作品の委嘱、初演は数多い。現在は東京を拠点に、演奏活動や古楽理論・奏法に関するセミナー等を企画。その他、松本市音楽文化ホール、東京藝術大学で講師を務める。
© 田中良知
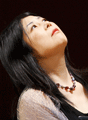
ピアノ:寺嶋陸也 Rikuya Terashima 1964年生まれ。東京藝術大学音楽学部作曲科卒、同大学院修了。オペラシアターこんにゃく座での演奏や、97年、東京都現代美術館でのポンピドー・コレクション展開催記念サティ連続コンサート「伝統の変装」、2003年パリ日本文化会館における作品個展「東洋・西洋の音楽の交流」等は高く評価された。06年にはタングルウッド音楽祭に招かれボストン交響楽団のメンバーと

テレマン:《無伴奏オーボエのための12の幻想曲》より 第1番 イ長調
G.P.テレマンは、J.S.バッハ、ヘンデルと同時代に北ドイツのハンブルクを拠点に活躍し、生前はバッハをしのぐ人気を得ていた(同時にバッハの功績をいち早く紹介したのもテレマンだった)。本作《12の幻想曲》は、もともとフラウト・トラヴェルソのために1732年頃に作曲された無伴奏の作品。さまざまな楽器に堪能だったテレマンは、なかでもトラヴェルソの腕に秀でていたと言われ、この作品も楽器の特性を活かした熟練の作法で書かれている。曲はヴィヴァーチェ/アレグロの2部構成。
J.S.バッハ:オーボエ・ソナタ ト短調 BWV1030b
原曲は、J.S.バッハがケーテンの宮廷楽長時代(1717〜23年)に作曲した「フルート・ソナタ ロ短調」。ケーテンの宮廷には優れた器楽合奏団があり、バッハはそのために多くの器楽曲を作曲している。「ブランデンブルク協奏曲」や「平均律クラヴィーア曲集(第1巻)」なども同時代の作品である。バッハは通奏低音付きのフルート・ソナタを6曲残しているが(ただし作曲者をめぐる真偽問題がある)、このソナタは、そのなかでも最も高雅な作品として知られている。曲はアンダンテ/シチリアーノ/プレストの3楽章構成。
シューマン:アダージョとアレグロ 変イ長調 op.70
原曲は、シューマンが1849年に作曲したホルン独奏とピアノのための作品(作曲時のタイトルは「ロマンスとアレグロ」)。19世紀は楽器の改良が進んだ時代であり、シューマンはこの作品に半音を自由に吹けるようになったバルブ・ホルンの独奏楽器としての可能性を託した。シューマンらしい抒情性と旋律美をたたえたアダージョ、技巧的で活気のある三部形式のアレグロからなり、ホルン以外の独奏楽器でもしばしば演奏される。
ミヨー:組曲《ルネ王の暖炉》op.205
新古典主義の作風を示すフランス六人組の一人ミヨーが、R.ベルナールの映画『愛の騎馬行列』のために作曲した映画音楽を7つの組曲に再編した、木管五重奏のための作品。映画音楽のほうは、オネゲル、デゾルミエール、ミヨーの三者で分担され、ミヨーが担当したのは15世紀にプロヴァンスを統治した名君ルネ・ダンジューの場面だった。表題にある「暖炉」とは、ダンジューが冬を過ごしたプロヴァンス地方のこと。ミヨーもまたプロヴァンスの生まれだった。
プーランク:管楽器とピアノのための六重奏曲
オネゲル、ミヨーらとともにフランス六人組を代表するプーランクが、木管五重奏とピアノのために1932年に作曲した作品(1937年改訂)。あらゆるジャンルに作品を残したプーランクだが、室内楽では特に管楽器を好み、管楽器独奏のための音楽を数多く作曲している。この作品はそれぞれの楽器に精通したプーランクならではの曲想と技巧が光っており、管楽アンサンブルのための楽曲のなかでも非常に完成度の高い作品となっている。アレグロ・ヴィヴァーチェ/ディヴェルティスマン、アンダンティーノ/フィナーレ(プレスティッシモ)の3楽章構成。
主催:東京・春・音楽祭実行委員会/Sony Music Foundation(公益財団法人ソニー音楽財団)
後援:札幌交響楽団 協力:野中貿易株式会社